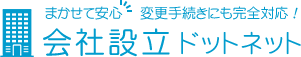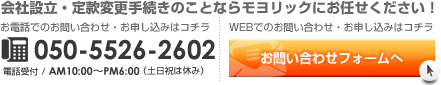【どこよりも分かりやすく解説】倉庫業登録申請マニュアルマニュアル
- 会社設立ドットネット TOP
- どこよりも分かりやすい!起業・独立開業ガイド
- 【どこよりも分かりやすく解説】倉庫業登録申請マニュアル
【電話受付時間】AM10:00~PM6:00(平日)
倉庫業登録申請

目次(もくじ)
倉庫業の概要:なぜ登録が必要なのか?
倉庫業を営もうとするものは、国土交通大臣の行う登録を受けなければなりません。(倉庫業法第3条)
人様のお荷物をお預かりして、その報酬をいただく行為を行うときに、国土交通大臣の登録を受けなければなりません。
「モノを預かる」ことを「業」として行うときに「登録」が必要なのです。
「物流の結束点として生産者と消費者を結ぶ」+「国民生活に欠かせない重要物資を大量かつ安全に保管」=『倉庫業の適切な運営の確保は我が国経済の安全にとって重要』
登録制にすることで、倉庫の施設設備規準を維持し、倉庫管理主任者による適切な管理を義務づけて、国民生活の安定をはかっているのです。
いい加減な事業者でも倉庫業を行えるということになれば、利用者に対して不足の損害をもたらし、結果として円滑な物流が阻害される恐れがあります。
また、誰でも彼でも倉庫業への参入を認め不良な倉庫業者が出現したときに大多数を占める善良な倉庫業者の信用を損なうことにもなりかねません。
そのための、倉庫施設設備規準の維持であり、倉庫管理主任者による適切な管理なのです。
たとえば、倉庫の火災発生事例では、倉庫業法による倉庫は、それ以外の倉庫に比べて極端に火災が少ないのです。
2003年の事例では、倉庫業法による倉庫の火災は5件なのに対し、それ以外の倉庫の火災は766件となっています。
火災に関する基準は建物の構造設備を規制する一般法である建築基準法、消防法等の基準に比べて厳しくなっています。
これは、他人の貴重な物品を預かる営業倉庫という観点から規定されているのです。
倉庫業の登録をすることで、信頼性が増すのです。
倉庫業法・建築基準法・都市計画法上の留意点
物件の建築、購入、賃貸の前に、まず確認しなければならないことが2つあります。
1.準住居地域を除く住居地域では、「倉庫業を営む倉庫」は原則として認められない。
都市計画法では、用途地域という規定があり、その用途地域が「準住居地域を除く住居地域」以外の用途地域、すなわち、準住居地域地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域で「倉庫業を営む倉庫」を営むことができます。
2.開発行為を有しない市街化調整区域では、「倉庫業を営む倉庫」は原則として認められない。
市街化調整区域とは、開発行為によらなければ、原則として何も建築することができません。
農地を守るために定められた区域であり、開発行為によって一定の要件を満たさなければならないのです。
※登録しようをお考えの物件が「倉庫業を営む倉庫」として使用できる施設になるかどうかは、事前に地方自治体、あるいは専門家に相談することをお勧めします。
倉庫業の規定云々の前に、建築基準法・都市計画法の規定を満たしていることが大前提だからです。
倉庫業法上の留意点
国土交通大臣の登録の登録拒否要件は次の3つです。
1.申請者等が欠格事由に該当する
- 1年以上の懲役等の刑を受けていること(又は執行後2年を経過していないこと)
- 登録の取消を受け、2年を経過していないこと
- 役員が1又は2に該当するものであること
2.施設設備基準に適合しない
3.倉庫管理主任者を確実に選任できると認められないこと
禁止されていることに、無登録営業の禁止(倉庫業法3条)[1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金]、無登録業者による誤認行為の禁止(倉庫業法25条の10)[50万円以下の罰金]、名称の使用制限(倉庫業法25条の7)[30万円以下の罰金]があります。
倉庫業の定義
倉庫業とは、「寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業」のこといいます。
倉庫業にあたらない例
1.寄託でないもの
- 消費寄託(預金など)
- 運送契約に基づく運送途上での一時保管(保管場、配送センターなど)
- 修理等の役務のための保管
- 自家保管
2.営業でないもの
- 農業倉庫
- 協同組合の組合員に対する保管事業
3.政令で除外されているもの
- 保護預り(銀行の貸金庫)
- 修理等の役務の終了後に付随して行われる保管
- ロッカー等外出時の携帯品の一時預かり
- 駐車場、駐輪場
倉庫業登録までの流れ・フローチャート
【事前準備】
手順1.運輸局への事前相談
取り扱う物品、施設の規模のことなどを確認、相談します。
まず、営業倉庫として登録できる物件の要件を理解し、確認しましょう。
手順2.物件選び
施設設備基準を考慮に入れて物件を選びます。
施設設備基準が倉庫業登録の最大のポイントとなるため、ここでは、不動産業者、建築業者、開発業者(開発行為を伴う場合)、物件所有者等との綿密な打ち合わせが重要となってきます。
手順3.地歩自治体との事前相談
倉庫業を営む倉庫として使用できるか相談します。
建築指導課、都市計画課等です。
事前に相談を行うことで、手続きはスムーズに進みます。
倉庫を建てるだけ建てて、いざ登録申請をしたら登録できないなんてことがないようにするためにも倉庫建設前にできるだけ早く相談すると良いでしょう。
【登録申請】
手順1.物件の選定
物件所有者、不動産業者、建築業者等と契約を結び、物件を決定していきます。
手順2.登録申請書作成・建築確認申請
建築確認申請では建物の用途の欄に、「倉庫業を営む倉庫」(コード番号08510)になっていれば倉庫業登録申請が可能です。
中古の物件を購入する場合は特に注意しましょう。
「倉庫業を営む倉庫」(コード番号08510)になっていない場合は、【事前準備】手順1.運輸局への事前相談のときに十分打ち合わせしておきましょう。
手順3.登録申請
運輸局へ申請します。運輸局では、説明聴取、実地調査を行い審査して、補正指導があれば指導があります。
倉庫業登録における倉庫管理主任者とは?
倉庫業者は、倉庫ごとに一人の倉庫管理主任者を置かなければなりません。
倉庫管理主任者の要件
- 倉庫の管理の業務に関して2年以上の指導監督的実務経験を有する者
- 倉庫の管理の業務に関して3年以上の実務経験を有する者
- 国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習を修了した者
- 国土交通大臣が1から3までに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者
倉庫管理主任者の欠格事由
- 1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 法第21条の規定による登録の取消を受け、その取消の日から2年を経過しない者
倉庫管理主任者の業務 (業務の総括に関すること)
- 倉庫における火災の防止その他の倉庫の施設の管理に関すること
- 倉庫管理業務の適正な運営の確保に関すること
- 労働災害の防止に関すること
倉庫管理主任者の業務(現場従業員の研修に関すること)
現場従業員に対する研修を企画し、実施する業務を指す。
倉庫施設の管理に関する事項
倉庫施設の管理に関する事項として、建物や設備、定温倉庫などのチェックを行わなければなりません。
【建物のチェック項目】
- 屋根
- 壁
- 床
- 基礎
- 出入り口、窓、防潮板
【設備のチェック項目】
- 換気設備
- 排水設備
- 消化器
- 消火栓
- 連結送水管
- スプリングラー
- 不活性ガス消火設備
- 火災報知設備
- 誘導灯
- 避難通路
- 受変電室の施錠
- 電線
- 分電盤
- 照明設備
- 通報、警報、表示設備
- その他設備
【定温倉庫のチェック項目】
- 出入り口
- 床、壁、天井
- 空調・給排水等設備
- 電気設備
- 貨物のはい付け
【構内のチェック項目】
- 野積み倉庫
- 擁壁
- コンクリート塀など
- 鉄柵
- 舗装
火災防止に関する事項
倉庫は大量に可燃物を収容していたり、出入り口や窓が普通の建物に比べたら少なかったりします。
また業務の性質上、大きな建物の割には従業員が少ないのが特徴的です。
こんな環境で、火災が起きたらどうなるでしょうか?発見が遅れがちになるでしょう。
通報や初期消火活動も遅れがちになります。
そのため、大きな損害を被らないためにも様々な対策を行う必要があるのです。
- 工事中の火災予防対策
- タバコによる火災予防対策
- 自然発火による火災予防対策
- 粉塵による爆発事故予防
- 漏電による火災事故
- 指定可燃物の爆発による火災事故対策
- 自動倉庫の火災防止対策
- 放火による火災事故対策
その他
地震に関する事項、倉庫管理業務の適正な運営に関する事項、労働災害に関する事項、現場従業員の研修に関する事項、などがマニュアルで定められています。
倉庫業登録の申請書類とその後の手続き
当ページでは、倉庫業登録に必要となる申請書と添付書類について解説しています。
倉庫業登録の必要書類一覧
1.倉庫業登録申請書
申請書はこちらのサイトからダウンロードできます。→http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/butsuryu05100.html
「5.営業開始予定日」には、相当な猶予期間がない限り「登録あり次第」と記入しましょう。
2.倉庫明細書
倉庫明細書の記載事項と図面等の添付書類の内容が合致していないと審査に入ることができないので注意が必要です。必ず確認しましょう。
冷蔵施設明細書などは、メーカー仕様書の数値の通り遺漏なく記入していきます。
3.施設設備基準別添書類チェックリスト
申請にあたって添付書類に遺漏がないかの確認できるようになっています。添付書類の目次として利用します。
4.登記簿謄本(土地・建物)
原本を添付します。
5.建築確認済証・完了検査済証
添付書類の中で最も重要です。
建築確認済証には、建築確認申請書の1面から5面を必ず添付します。
建築確認済証と完了検査済証の2つで1セットです。番号に間違いはないか確認しましょう。
用途の欄のコード番号が「08510」(倉庫業を営む倉庫)となっているかを確認しましょう。
「08520」(倉庫業を営まない倉庫)では原則として申請を受け付けてもらえません。
6.その他図面以外の書類
例えば、
- 警備状況説明書/警備契約書
- 構造計算書
- 平均熱貫流率の計算書
- 照明設備表
- 消防用設備等検査済証
- 食品衛生法第52条第1項の営業許可証といった公の証明書
- 冷凍能力が熱損失以上あることがわかるメーカー仕様書、冷却試験結果表、通報機等の詳細が明示された図面
- 温度管理システム仕様書
など。
7.倉庫付近の見取図
市販の地図でOKです。
8.倉庫の配置図
敷地内にある全ての施設及び設備の状況を明示します。縮尺は原則1/300~1/1200です。
9.平面図
明瞭さが求められています。色分けをして明示しましょう。縮尺は原則1/50~1/200です。
10.立面図
東西南北4面が少なくとも必要です。縮尺は原則1/50~1/200です。
11.断面図
東西・南北の2面が少なくとも必要です。縮尺は原則1/50です。
12.矩形図等
矩形図等とは、倉庫の屋根、軸組み、外壁及び荷ずり並びに床の構造の詳細を記載した矩形図、断面詳細図などのことです。倉庫明細書に記載された主要構造を審査する上で最も重要な図面です。
13.建具表等
建具表等とは、倉庫に設けられた建具の構造の詳細及び位置を記載した建具表・建具キープランなどのことです。
14.倉庫管理主任者関係書類
倉庫管理主任者の選任は必須です。
15.法人登記関係等書類・戸籍抄本等
法人の場合は、「商業登記簿謄本」個人の場合は、「戸籍謄本」を添付します。個人の場合は「資産調書」を作成します。
16.宣誓書
欠格事由に該当しない旨の宣誓書を作成します。
17.倉庫寄託約款
倉庫寄託約款は営業を始める30日前までに届出が必要ですが、登録申請の際に添付すれば届出を省略することができます。
※作成部数は、会社控え1部、支局等用1部、運輸局等用1部となってます。(所管面積が10万㎡を超える場合は、国土交通大臣用にもう1部作成)
倉庫業者となってすぐに必要な手続き
1.登録免許税の納付
納付書に基づき9万円(新規登録の場合)
2.料金の届出
保管料、荷役料等の料金を設定又は変更した場合(実施後30日以内に届出)
毎期必要な手続き
1.期末倉庫使用状況報告書の提出(当該四半期経過後30日以内に提出)
2.受寄物入出庫高及び保管残高報告書の提出
その他手続き
- 変更登録(事前登録)
- 軽微変更届(30日以内届出)
- 寄託約款の届出(30日前届出)
- 倉庫証券の発行許可(事前許可)
- 営業の譲渡譲受届出(30日以内届出)
- 法人の合併分割届出(30日以内届出)
- 発券倉庫業者の営業の譲渡譲受認可(事前認可)
- 発券倉庫業者の法人の合併分割認可(事前認可)
- 相続届出(30日以内届出)
- 発券倉庫業者の相続認可(60日以内認可)
- 営業廃止の届出(30日以内届出)
- 発券業務廃止の届出(30日以内届出)
- トランクルームの認定(事前認定)
- 認定トランクルーム変更届出(事前届出)
- 認定トランクルーム廃止届出(30日以内届出)
- 料金設定変更届出(30日以内届出)
- 役員選任・変更届出(30日以内届出)
- 倉庫証券株式変更届出(30日以内届出)
- 事故発生の届出(14日以内届出)
- 倉庫証券発行回収高・流通高報告(4月30日報告)
こちらのサイトから申請書をダウンロードできます。→http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/butsuryu05100.html
メインメニュー
Topics!!
【よく読まれている記事】
株式会社設立編
【よく読まれている記事】
資金調達・税金編
株式会社設立ガイド
起業・独立開業ガイド
定款変更ガイド
起業と社会・労働保険
合同会社(LLC)設立
一般社団法人設立
有限責任事業組合(LLP)設立
会社設立と建設業
会社設立と不動産投資
会社設立と介護事業
会社設立と農業
Copyright (C) 2019 行政書士法人MOYORIC(モヨリック) All Rights Reserved.
掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。