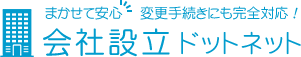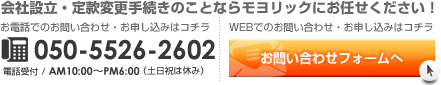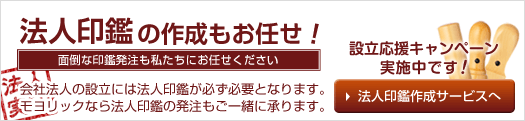このページを見ればまるわかり!株式会社設立手続きの流れ・フローのポイント解説。
- 会社設立ドットネット TOP
- いちばん詳しい!株式会社設立ガイド
- 株式会社設立までの流れ
【電話受付時間】AM10:00~PM6:00(平日)
起業支援専門行政書士が1から10まで徹底解説。
まるわかり。株式会社設立の「流れ」と「手続き」

はじめに
ネット上には、格安や0円での設立代行業者が乱立していますが、後先を考えずに安易な手続きをしてしまったが為に、書類の内容や手続きに不備が見つかり、役所で補正を受けるケースが増えています。
運良く補正には引っかからず、ひとまず設立はできたものの、許認可や資金調達、銀行口座の開設の場面になってストップがかかることも多いようです(定款に必要な文言がないor余計な文言が入っている等々の理由による場合が多い)。
一旦、定款認証を受け設立登記をしてしまったら、簡単には書類の修正はできません。認証手数料や登録免許税を改めて払い直さなければなりません。これらの実費を払い直してまで手続きをやり直すのは現実的ではありません。
とはいで、設立登記完了後の変更手続きも、素人が速やかに、かつ、簡単にできる類の手続きではありません。お金も手間も、時間も掛かります。
手続きに必要なルールを理解することなく設立したが為に、無駄なコストが掛かってしまうケースは、実に多いのです。
設立を急いでいるときこそ、気を付けなければならない。
許認可の取得や銀行融資、又は取引先との関係などで、とりあえず急いで設立をしなければならないといったケースも出てくることでしょう。
しかしながら、急いで設立をしなければならない場合も、急がば回れです。
いくら急いでいるからといって、適当に書類を作ってはなりません。
書類の作り方や作成の順番を間違えたり、資本金の振り込むタイミングを間違えたり。印鑑の着き方を間違えたり。何度も何度も役所に問い合わせをしたり、足を運ぶ羽目になります。結局は時間がかかってしまうのです。
であるならば、最初から手続きの内容や流れを一から把握しておいた方がよいでしょう。
急いでいるからこそ、慎重に手続きを進めて、一発で完璧な会社を作る方が結果としてビジネスは上手く回りはじまるのです。
株式会社の設立に関係してくる官公署は多岐に渡ります。
- 「公証役場」で提出しなければならない書類は?所要時間は?
- 「法務局」で提出しなければならない書類は?所要時間は?
- 「税務署」へ提出しなければならない書類は?所要時間は?
- 「都道府県税事務所」「市区町村役場」へ提出しなければならない書類は?所要時間は?
その他にも、年金事務所・労働基準監督署・ハローワークなど、ざっと挙げただけでも、これだけの役所が絡んできます。
あなたがこれから始める事業が許認可業種の場合は、更に監督官公庁への許可申請(建設・宅建・飲食・介護etc)が必要になります。
これらの役所での手続き、全てを把握してらっしゃいましたか?
当ページをお読みいただき、株式会社設立手続きの流れと、各手続きのポイントを把握し、スムーズな設立を行う為の、最低限の知識を仕入れていただければと思います。
ご自身で全ての手続をされる場合はもちろんのこと、行政書士、司法書士、税理士などの専門家に手続きを依頼する場合でも、これから当ページで解説していく知識を頭に入れておくことで、専門家とのやり取りもまたスムーズに行き、無駄も省けます。
あなたの人生において、そう何度も株式会社を設立することはないと思います。
だからこそ、失敗のない、確実な株式会社設立を行いましょう。
スタートアップでいきなり躓くのは避けたいですものね^^;
なお、こちらのページ「株式会社を設立するには?【株式会社を作る際に決めなければならない8つの事項】」もあわせてご覧いただければ、よりいっそう、理解が深まります。
では、さっそく見て行きましょう!
【関連ページのご案内】
株式会社設立のメリットほか、会社設立と同時に融資を考えている方、起業・独立開業ノウハウをお知りになりたい方は、これらのページもぜひご覧ください。
【目次】株式会社設立(発起設立)は全部で8ステップ!
- STEP1 まずは株式会社の基本事項を決める。決める事項はたったの8つ。
|-(1)商号を決める
|-(2)事業目的を決める
|-(3)本店所在地を決める
|-(4)事業年度を決める
|-(5)資本金を決める
|-(6)出資者(設立時株主)を決める
|-(7)株式譲渡制限の有無を決める
|-(8)機関設計(役員構成)を決める
|-(その他の検討項目)ウェブサイトを持っているならWEB決算公告がお得? - STEP2 設立手続きに向けて、事前の準備を行う
|-準備その1:発起人及び役員(取締役等)に就任する人の印鑑証明書を取得する
|-準備その2:類似商号の調査(管轄法務局)
|-準備その3:設立登記申請に必要となる会社代表者印(法人実印)を作成する
|-準備その4:事業目的の事前確認(管轄法務局) - STEP3 定款を作成して公証人役場で定款認証を受ける
|-定款を作成する
|-公証役場で定款認証を受ける - STEP4 役員の就任承諾書を作成する
|-就任承諾書を作成する
|-設立時代表取締役選定決議書を作成する - STEP5 資本金を払い込む
|-払込証明書を作成する
|-調査報告書を作成する(現物出資時のみ)
|-資本金の額の計上に関する証明書を作成する(現物出資時のみ) - STEP6 管轄の法務局で株式会社設立登記の申請を行う
|-登記申請書を作成する
|-別紙(登記すべき事項)及び印鑑届出書を作成する - STEP7 税務署などへ株式会社設立後の各種法人設立届出を行う
|-登記事項証明書、印鑑証明を取得する
|-税務関係の届出を行う
|-社会保険・労働保険関係の届出を行う - STEP8:株式会社名義の銀行口座を作ろう!
|-法人名義のクレジットカードも作ろう! - 設立手続きQ&A
Q.会社の商号は自由に決めていいのでしょうか?
Q.事業目的を決めるときの注意点はありますか?
Q.会社の住所はどこでもいいのでしょうか?
Q.資本金の決め方は?
Q.誰が出資してもいいのでしょうか?
Q.資本金を払い込む銀行口座は新たに開設したほうがよいのでしょうか?
Q.資本金を払い込む銀行口座はネット銀行でも大丈夫でしょうか?
Q.譲渡制限を付けないとどうなりますか?
Q.会社代表者印(法人実印)はどこで作ったらいいのでしょうか? - 設立登記完了後の手続きQ&A
Q.会社設立後に必ず行う手続きを教えてください。
Q.税務署へは「法人設立届出書」を提出すればいいだけですか?
Q.会社の銀行口座は会社設立後でないと開設できませんか?
Q.一人会社ですが、会社設立後は社会保険に加入するのでしょうか?
Q.従業員を雇ったらどのような手続きが必要ですか?
Q.社会保険の加入が会社設立後5日以内とありますが、遅れると罰則はありますか? - まとめ
|-設立後の適正かつ円滑な事業経営には専門家が不可欠。あなたにぴったりの専門家(税理士・社労士等)を探そう。
※既に個人で事業をされていて、株式会社による法人成りを行う方は、こちらも合わせてご覧ください。個人事業の廃業届出を提出する必要があります。
STEP1 まずは株式会社の基本事項を決める。決める事項はたったの8つ。
まず、株式会社の基本事項である商号・事業目的・本店所在地・役員構成などを決めていきます。
これらの事項は、主に発起人(設立時株主)であるあなたが決定します。発起人が複数いる場合は、過半数以上で決定しますが、通常は全会一致で決まると思います。
なお、これらの基本事項の中には、設立時の役員で決められる事項もありますが、発起人がこの時点で一度に決めてしまう方が、後々の手続きや書類作成がラクになります。
(1)商号を決める
株式会社の「名前」「名称」です。
法律用語では「商号」と呼ばれ、基本的には自由に決めることができます。
漢字・ひらがな・カタカナ・アルファベット・アラビア文字・その他の記号(コンマ・ハイフン・ピリオド・中点・アポストロフィーなど)が利用可能です。
同一住所に同一の商号がある場合は、登記できません。
商号を決定する際は、会社法だけでなく、不正競争防止法等の法律にも注意する必要があります。
法務局での商号調査(同一住所に同一の商号が無いかの確認)に加えて、グーグルなどの検索エンジンを使って、似たような会社名が無いかも念のため確認しておきましょう。
商号調査は、商業登記を扱っている登記所が最寄りにある場合はそこで済ましてしまうのが一番ですが、遠方にある場合は、法務省サイトからオンラインで行うことも可能です。ページはこちらです(利用登録は必要)。→オンライン登記情報検索サービスを利用した商号調査について
商号を決める際は、マーケティングの要素(自社の商品名やサービス名をそのまま商号にしてしまう会社さんもいらっしゃいます)に加えて、事業に対する思い入れ・呼びやすさ・親しみやすさなども考慮されると良いでしょう。
なお、会社のホームページの開設を考えていて、ドメインに会社名を入れたい場合は、その会社名でドメインが取れるかどうかも、事前に確認しておくとよいでしょう。「お名前ドットコム」や「ムームードメイン」などのドメイン販売サイトで簡単に確認ができます。
ドメインは英数字しか使えませんが、英語表記の会社名にするケースだと、そのままのスペルでドメインが取れるかもしれません。
ドメインはインターネットの世界の上での住所のようなもので、1つとして同じものはありません。
オリジナルのドメインは早いもの勝ちです。商号が決まったら、すぐにドメインを取っておきましょう
ドメイン販売会社は数多くありますが、このムームードメインは低価格で管理もしやすく、普通の会社がドメインを取得する分にはここで十分です(ムームードメイン![]() )。
)。
(2)事業目的を決める
事業目的は「何をする会社なのか」を対外的(取引先、顧客、金融機関など)に明示するものです。
原則として、目的の範囲外の事業はできないので、当面は予定していなくても、将来行いたい事業内容があればそれも挙げておくとよいでしょう(設立後に事業目的を追加する場合、法務局で変更登記手続きが必要になります。登録免許税も3万円掛かります)。
他人から見て、どんな事業をしているか明確に分かるように「具体的」であること、行う業務に「違法性がない」こと、更には「許認可が必要な業務について正確な記載がされているか」ということに、考慮して決めてください。
事業目的例・サンプルの検索は、弊社の別サイトにはなりますが下記ページにございます。事業目的作成時の参考にしてください。
目的の数については制限はありませんが、あまりに多いのは考えようです。何をメインに業務を行っている会社か、取引先や顧客にとって、判然とせず、不信感を抱かれる場合があります。
また会社設立後、あるいは設立と同時に日本政策金融公庫や銀行などからの融資を考えている場合は、特に注意が必要です。
事業内容はあれもこれもではなく、中心となる事業に絞って定めましょう。
メガカンパニーでもない限り、登記簿謄本に様々な業種が30個も40個も羅列されている会社の印象はよくありません。
金融機関によっては、目的に記載をされているだけで融資がNGとなる文言などもありますので、注意しましょう。
事業目的を適当に決めてしまうのは絶対にNGです。
会社設立後に会社運営上、何らかの支障が出てしまうケースで、最も多いのが「事業目的の記載不備」です。
公証人や法務局でも入念にチェックされる項目のうちの1つでもあります。
法務局での事前確認はもとより、許認可が必要な業種を営むのであれば、事前に必ず管轄の行政窓口に問い合わせを行い、「記載に必要な文言はこれで間違いないか?」、確認を取っておきましょう。
参考までに許認可が必要な主要業種の目的決定時の注意点を掲載しておきますので、該当される方はぜひご一読いただければと思います。
【参考ページ】
(3)本店所在地を決める
会社の本店とは、会社の主たる営業所のことで、会社の本店所在地は、「会社の住所」です。
この本店所在地をどこにするかによって、申請先の法務局が決まります(管轄と言います)。
「(1)商号を決める」でも軽く取り上げましたが、この住所に同一の商号がなければ登記が可能です。
住所地としての実態があればどこでもOKです。実際に法務局が本店所在地を見に来ることはありません。
自宅(持ち家or賃貸)、テナント、レンタルオフィス、バーチャルオフィス、コワーキングスペースなどで登記が可能です。
持ち家で一軒家の場合は登記についてはまず問題ありませんが、分譲マンションや賃貸マンションで登記を考えている場合は、事前に管理規約や契約書の中身を確認しておきましょう。
商用利用不可・会社登記不可となっている可能性があります。
【レンタルオフィス・バーチャルオフィスの注意点】
レンタルオフィス・バーチャルオフィス・コワーキングスペースに関しては設立登記自体は可能です。が、注意すべき点も非常に多いので、気をつけてください。
銀行によっては銀行口座の開設がNGであったりと、思ってもないところで大きな不利益を被る可能性があります。
今の時代、銀行口座が作れなければ商売はできませんからね・・・。
レンタルオフィス等で登記を考えている場合は、レンタルオフィス提供元の会社への確認はもとより、口座開設を考えている銀行窓口にも問い合わせをしておいた方が無難です。HPにそのあたりの情報を掲載している銀行もあります。
金融機関から事業資金の借り入れを考えている場合も、注意が必要です。レンタルオフィス等はNGとしている金融機関も見受けられます。管轄にも依りますが、社会保険の加入にも苦労することがあるようです。
その他、許認可が必要な業種、例えば建設業や介護、不動産業では、多くの場合事務所に関する要件(間取り、事務所としての体裁が整っているかどうか等)が定められていますので、こちらも事前確認が必須です。
【本店所在地と自治体制度融資の関係性】
資金調達において自治体の制度融資などの利用を考えている場合、本店所在地によって自治体の管轄が変わります。自治体によって融資条件等も異なります。
株式会社の設立と同時に制度融資の利用を行う場合は、融資条件なども考慮して本店所在地を決めると良いでしょう。
なお、ここまでは会社法やその他許認可法令に関しての解説でしたが、会社のオフィスを決めるにあたっては次のような事項もまた重要になってきますので、参考にしてください。
- 家賃・管理費(資金繰りに大きな影響を及ぼします)
- 敷金礼金・保証金の有無
- インターネット接続環境が整っているか(どこのプロバイダーに入れるかによって毎月の通信費や電話代が大きく異ります)
- 日当たり・周囲の環境
- 顧客アクセス
- 自分と従業員の通勤アクセス
- 管理人及び警備員の有無(セキュリティ対策上重要です。セコムやアルソックなどに頼むと結構掛かります)
- トイレや給湯室の清潔さ(意外に重要です)
- 24時間利用可能か etc
会社の職場環境は生産性の向上その他財務など様々な点で、経営に影響を及ぼします。
会社法その他の法令に加えて経営環境も考慮するのであれば、本店所在地は慎重に慎重を重ねて、選ぶとようにしましょう。設立後すぐに引っ越しとなれば、引越し費用もバカになりませんからね。。。
会社設立後に本店所在地を変更するには、法務局での変更登記が伴います。この登記には登録免許税だけで3~6万円(管轄内移転は3万円、管轄外移転は6万円)かかります。
コロコロと会社を移転するのは資金的にも得策とは言えません。
(4)事業年度を決める
会社は通常1年ごとに会計の区切りを設けて、申告の為に一旦会計を締めます。これを「決算」といいます。この決算期間を「事業年度」といい、開始月は自由に決めることができます。
ただし、1年を越えることができないので、例えば「毎年4月1日」から事業年度を開始にするのであれば、「翌年3月31日」が決算日となります。
なお、事業年度の末日が決算日になるのですが、この末日は月末に合わせておきましょう。まれに誕生日が1月28日だからとか、記念日や思い入れのある日だからと、中途半端な日付を決算日にする方もいるのですが、締めのタイミングや決算を組むのに大変苦労してしまうようです。また、2月末日決算の場合はうるう年にも気をつけましょう。
税務署への申告自体は決算日から原則2ヶ月以内に行わなければなりませんので、事業の繁忙期と重ならないように設定するものひとつです。繁忙期が予測できる場合は、売り上げが一番上がる前の月を決算月にするもの良いでしょう。そうすれば、1年を通して余裕を持って節税対策を行うことができます。繁忙期の前の月を決算月にする方法は、決算事務と重なることもなく、かつ、節税対策が行いやすくなり、一石二鳥です。
法人の決算申告(確定申告)は個人事業主時代のように、素人が自分でできる類の手続きではありません。
決算内容によって税額も決まるわけですから、失敗も許されません。時間もかかります。株式会社を設立した場合は、税理士と顧問契約を結ぶのはマストと覚えておきましょう。もちろんですが、税理士に依頼すると決算代行料が掛かります。
税理士の価格形態は月額顧問料+決算代行料の場合と、月額顧問料に決算代行料も含まれている場合とがあります。
前者の場合は、決算代行料がかかりますから、株式会社の設立1期目の決算はできる限り先延ばしにした方がコストを抑えることができます。
ですから、例えば設立が1月だとしたら、事業年度の末日を12月と決めておくことで、一期目の決算までの期間を最長化することができます。面倒でかつコストが掛かる決算を先送りできるというわけです。
また、諸条件はありますが、法人設立後、最大2期(約2年間)は消費税の免税を受けれらるケースもありますので、特に決算期についてこだわりがない場合は、設立1期目は最大限先送りしておくのがベターかと思います。
日本は3月決算の会社や役所が多いという理由だけで、特別な意味もなく3月決算にしてしまうような愚かな行為は止めましょう。
(5)資本金を決める
会社が事業を開始するときに、自由に使える運転資金を言います。設立時に決めておく必要があります。資本金はいくらでもかまいませんが、多ければ多いほど、設立当初の資金繰りが楽になります。資本金の出資方法には、お金以外の「物」による出資も可能です。
資本の額を決める際は、運転資金、対外的・社会的信用、節税面など、あらゆる面を考慮して決定します。
資本金の額の決め方については、当サイト内のこちらのページもぜひ参考にしてください。
全国と弊社顧客の資本金額の相場・平均値や、資本金と税金・資金調達・許認可との関連性等について、詳しく解説しています。
【参考ページ】
(6)出資者(設立時株主)を決める
株式会社設立時の出資者(発起人)は、設立後に「株主」となります。
出資者が会社に対して出資をし、その見返りとして会社が出資者に配当(利益還元)をするということになります。
株主は議決権を持ちます。株主は株主総会を構成し、会社の重要事項を決めていきます。代表的なもので言うと、定款変更、役員の選任解任、役員報酬額の決定などです。
なお、法人でも個人でも出資者(株主)となることができます。また、外国の方や未成年でもなることが可能です。
(7)株式譲渡制限の有無を決める
株式会社が発行する株式は自由に譲渡できるのが原則です。
しかし、株式の譲渡による取得について、定款に記載することにより制限を設けることができます。
これは会社の乗っ取り防止や会社の望まない者に株式が譲渡されるのを避けるために置くものです。
大会社・大企業でないかぎり、株式譲渡制限は付けるのが一般的です。全国の中小企業の大半は株式譲渡制限会社です。
これから会社を作る方も株式譲渡制限会社にしておけばまず問題ありません。
(8)機関設計(役員構成)を決める
会社の意思決定や運営・管理などをする機構や地位のことをいいます。
具体的には「取締役」や「取締役会」、「監査役」や「監査役会」などです。一般的な中小企業であれば「株主総会」と「取締役」は必ず設置しなければいけません。
一人オーナ会社の場合の機関構成は必然的「株主総会」と「取締役」の2つになります。
取締役が3名以上、監査役が1名以上いるのであれば、「株主総会」と「取締役」に加えて「取締役会」の設置が可能になります。
ここで、具体的に誰が取締役になるのか?監査役になるのか?代表取締役には誰がつくのか?を決めます。
取締役は欠格事由に該当しなければ誰でも就任できます。未成年でも構いません。取締役の人数に制限はなく、1名以上居ればOKです。また代表取締役を複数名とすることも可能です。
(その他の検討項目)ウェブサイトを持っているならWEB決算公告がお得?
株式会社には公告義務が課せられています。公告とは、読んで字のごとく「公に告げる」ことを意味します。
毎年の決算が確定したとき、合併や解散を行うとき、資本金を減らすとき等の場合に、「必ず」公告をしなければならない。と、会社法に定められています。
公告を行う方法は3つ。官報・新聞・電子公告、いずれか方法になります。
株式会社の設立時に、これら3つの中から公告方法を選択し、登記を行います。通常は一番メジャーで使い勝手も良い官報を選択します。
中小企業は決算公告がメイン
合併や解散などは中小企業が行うことは稀ですので、あまり気にする必要もないのですが、決算公告(中小企業は貸借対照表を公告する)については、会社規模に関わらず株式会社であればすべての会社が毎年、行わなければなりません。
ですが、この決算公告を官報や新聞に掲載するとなると決して安くはない費用が発生します。
現在も、決算公告義務があるにも関わらず、義務を果たしてない会社が大半を占めるのですが、その理由は面倒臭いのとお金が高いからです。
ですが、これではいけません。決算公告義務違反は100万円以下の過料に処せられます。今はお咎めもありませんが、将来どうなるかは誰にも予想できません。
「ほとんどの会社がやってないんだからうちも大丈夫だよ」ではなく、いつ過料に処せられてもおかしくない状況には変わりはないのですから、きちんと決算公告は行いましょう。
決算公告を安く済ませる方法
決算公告は自社WEBサイト上に公開する方法で行えば、費用は0円で済みます(とは言え、決算公告をWEBで行う場合、最低5年間の掲載義務が課せられませすので、単純計算で5年以上分のドメイン・サーバー代が掛かります。)。
ホームページを持っている会社、あるいはこれからホームページを作ろうと考えている会社であれば、この方法を使わない手はありません。
デメリットもある
当然ですが、WEBサイトに自社の決算をさらけ出す形になります。公告という形に変わりはありませんが、官報は一般の方はほとんどチェックしていません。官報の存在すら知らないという方が大半を占めます。
ですから、決算の内容をあまり見られたくないという場合は、やはり官報を選択しておくというのも1つです。
あと、あまりWEBが得意で無い方にとっては、WEBサーバーに資料をアップする作業ですら、億劫でしょう。それを毎年行わなければなりません。WEB自体が苦手な人は、費用が安いからといって安易にURLを登記するのは止めておきましょう。WEBサイトの管理を長期に渡って続けていく自信がない場合は、官報にしておくほうが無難です。
株式会社設立と同時にWEB決算公告の登記を行いたい場合
会社設立と同時にWEB決算公告を選択する場合は、設立登記申請日までにURL(ドメイン)を取得しておく必要があります。ホームページのURLを登記しなければならないからです。
なお、WEB決算公告を選択した場合、定款に定める公告の方法も「電子公告」にしないといけないのでは?と勘違いされている方も多いのですが、定款への記載、及び、登記事項も「官報」のままでOKです。
なお、WEB決算公告登記は設立した後でもいつでも登記することができますので、設立後にある程度時間とお金に余裕ができたときに、変更登記を行うのも1つです。
STEP2 設立手続きに向けて、事前の準備を行う
上記STEP1で基本事項を決めると、自ずと必要となる書類等も決まってきます。
商号が決まれば、商号調査を行い、法務局へ届け出る印鑑を作成できます。
役員構成が決まれば、取締役の印鑑証明書を取得。といったようにです。
では、それぞれ見て行きましょう。
準備その1:発起人及び役員(取締役等)に就任する人の印鑑証明書を取得する
発起人となる方、また、取締役に就任される方全員の個人実印の「印鑑証明書」が必要になります。
市区町村役場で取得できますが、有効期限は発行後3ヶ月以内となっていますのでご注意ください。
まだ印鑑登録をしていない場合は、まずは印鑑登録をしてから印鑑証明書を取得します。通常は窓口に出向けばその日のうちに印鑑登録と印鑑証明書の取得を同時にできますが、念の為事前に確認を取っておきましょう。
準備その2:類似商号の調査(管轄法務局)
STEP1で考えた商号が同一住所にないか、また、類似しているものがないかを調査します。
この調査は、本店予定地の管轄法務局に備え付けられている「商号調査簿」を閲覧すれば簡単にできます。
最近は商号調査端末が備え付けされている法務局も増えてきましたので、端末がある場合は更に簡単に調査できます。
準備その3:設立登記申請に必要となる会社代表者印(法人実印)を作成する
登記を行う際に提出する申請書に押印する会社の代表者印です。
代表印は、登記申請を行うときに一緒に届け出をしなければなりません。印鑑は申し込んでからできあがるまで時間がかかる場合もあるので、類似商号のチェックが済み次第、早めの準備をおすすめします。
弊社でも法人実印を販売しております。最短即日発送です。
準備その4:事業目的の事前確認(管轄法務局)
STEP1で挙げた事業目的で、登記が可能か登記申請をする前に調査します。
それぞれの法務局(担当登記官)によって正否が異なりますので、本店予定地の管轄法務局できちんと確認しておきましょう。
事業目的の確認は、法務局の相談窓口まで出向くか、若しくは、電話相談を受け付けている法務局であれば電話での確認も可能です。
その他、許認可等を得るために必要な事項も確認しておくべきです。許認可が必要な業種で代表的なものの例を挙げておきます。建設業、介護事業、人材派遣、飲食店、宅建業などです。
【関連記事】
STEP3 定款を作成する・公証人役場で定款認証を受ける
STEP1で基本事項を決め、STEP2で必要書類の収集や事前調査等、準備は終わりました。いよいよ会社の根本規則である定款の作成と認証に移ります。では、見て行きましょう。
定款を作成する
定款とは、会社の目的、内部組織、活動に関する根本規則を記載したものです。
いわば、その会社の「憲法」のようなものです。定款には、必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」があるので、その漏れがないようにします。
その他には、会社の基本ルールを記載しておきます。また、なるべく会社法の条文の用語に即して作成するので、重要な条文には目を通しておく必要があります。
【株式会社定款の絶対的記載事項】
- 商号
- 目的
- 本店の所在地
- 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
- 発起人の氏名及び住所
- 発行可能株式総数
定款作成に関しては、下記ページも参考にしてください。
公証役場で定款認証を受ける
株式会社の設立に際して、発起人が最初に作成した定款(原始定款)は公証人の認証を要します(設立後の定款変更時は不要です)。
定款認証は、「会社の本店所在地を管轄する法務局又は地方法務局の所属公証人」が扱うこととされています。
実際には、会社の本店と同一都道府県にある、最寄りの公証役場の公証人から認証を受けるのが便利です。交通費の節約、移動時間の短縮になります。
公証役場での定款認証手続きの詳細は下記ページを参照ください。
なお、紙媒体ではなく、定款を電子化して認証を受ければ、印紙代4万円が不要になります。
STEP4 役員の就任承諾書を作成する。
就任承諾書を作成する
設立会社で代表取締役・取締役・監査役に就任予定となる方に、就任の意思があるかどうかを確認する必要があります。
就任を承諾したことを確認した証明となるのが「就任承諾書」です。新たに就任される方の住所・署名・捺印をし、設立登記申請時に提出します。
設立時代表取締役選定決議書を作成する
取締役会設置会社は、設立時代表取締役を選定しなければなりません。
この設立時代表取締役は1名に限られているわけではありませんので、設立時取締役全員を代表取締役とすることも可能です。設立時代表取締役は取締役会で選定されますので、その書類を作成し設立登記申請時に提出します。
STEP5 資本金を払い込む
次に、出資者(発起人)が出資金を振り込みます。
通常はこの振込金額の合計額が設立する株式会社の設立時資本金となります。資本金の払込が終われば、それを証明するための書類を複数作成します。
払込証明書を作成する
「払込証明書」とは、発起人代表者個人の口座に、出資者が資本金の払込みを行い、代表者がその払込みがあったことを証明するものです。
払込みがあった旨を記載した書面に、預金通帳の写しを合綴したものを準備します。
調査報告書を作成する(現物出資時のみ)
金銭以外で出資をすることを「現物出資」といいます。
その出資物に不当に多くの株式が付与されぬよう、検査役の調査を受けなければなりません。
いくつかの例外のひとつに、定款に記載価額の総額が「500万円以下」である場合は調査が免除されるというものがあります。
一般的な中小企業はこの対象となり、調査不要となることが多いです。
資本金の額の計上に関する証明書の作成
会社が払込を受けた金銭・現物出資財産から、会社が負担するべき設立にかかった費用等を引き、登記簿に記載される「会社の資本金」を計算する書類です。
現物出資がある場合に添付が必要となる書類です(金銭出資のみの場合は不要)。
STEP6 管轄の法務局で株式会社設立登記の申請を行う
いよいよ、最終段階に入ってきました。
会社は、定款認証を受け、管轄の法務局に設立登記申請書を提出することによって、法的に成立します。では、見て行きましょう。
登記申請書を作成する
株式会社の設立登記申請は、会社の代表者が「会社の本店の所在地を管轄する登記所」において行うことになります。
株式会社の設立登記申請書には、法定の書面を添付する必要があります。
これらの書類の作成方法は、法務省民事局のホームページに基本様式が掲載されています。会社代表者の代理人(司法書士・弁護士)による申請でも可能です。
別紙(登記すべき事項)及び印鑑届出書を作成する
登記すべき事項をパソコン等で作成した別紙を準備します(または、登記すべき事項をCD-Rなどの磁気ディスクに記録して提出することもできます)。
同時に、あらかじめ作成しておいた会社の代表印を登録するために、登記申請と同じ管轄登記所に「印鑑届出書」を作成して提出します。
「印鑑届出書」の用紙は法務局に無料で備えられていますし、法務省ホームページからダウンロードすることも可能です。
【すべての株式会社において必ず登記しなければならない事項】
- 商号
- 本店及び支店の所在地
- 目的
- 資本金の額
- 発行可能株式総数
- 発行済株式の総数並びにその種類及び数
- 取締役の氏名
- 代表取締役の氏名及び住所
- 公告方法についての定め
なお、法務局に申請書類を提出した日が、会社の設立日になります。
実際に登記が完了して、法務局で登記事項証明書が取れるようになるには少し時間がかかりますので、申請窓口で、いつ登記が完了するかを確認しておきましょう。
申請書類に不備などが見つからず、補正が入らなければ、通常は一週間から10日で登記完了します。
STEP7 税務署などへ株式会社設立後の各種法人設立届出を行う
登記が完了すれば、会社の登記事項証明書や印鑑証明書が取得できるようになりますが、設立手続きはそれで終了ではありません。
税務署や社会保険事務所への法人設立届等の提出がまだ残っています。
では、見て行きましょう。
登記事項証明書、印鑑証明を取得する
設立登記が完了した後、①税務署等の税務関係機関、②労働基準監督署、公共職業安定所、③社会保険事務所へそれぞれ必要な届け出をしなければなりません。
その際に、登記事項証明書(登記簿謄本)と法人印鑑証明書の原本が必要になってきますので、取得しておかなければなりません。
税務関係の届出を行う
会社を設立し営業活動を開始すると、国には法人税等を納付する必要があるため、税務署には各種の届出書などの提出をしなければなりません。
また、都道府県と市町村には、地方税である「法人住民税」と「法人事業税」を納付することになることから、都道府県税事務所と市区町村役場の双方に、それぞれ法人設立届出書を提出することを要します。
役員報酬の設定や、源泉徴収などの関係もありますから、税務関係については、専門家である税理士に相談しておいた方がよいでしょう。
社会保険・労働保険関係の届出を行う
株式会社は、すべて「社会保険」への加入が義務付けられています(社会保険とは一般に「健康保険」と「厚生年金保険」です)。
よって、会社設立後は速やかに、社会保険事務所に届書等を提出する必要があります。
また、労働者を1人でも雇った会社は、労働保険の適用事業となり、労働保険を納付することを要します(労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」との総称です)。
この場合には、労働基準監督署と公共職業安定所等に書類を提出することとなります。
STEP8 株式会社名義の銀行口座を作ろう!
ここまでで全ての法律手続きは終了ですが、これではまた営業ができません。
株式会社名義の銀行口座を作りましょう。銀行口座の開設に要する時間は各銀行によってまちまちです。1週間~10日以上かかる銀行もあるようです。早め早めに準備をしていきましょう。
振り込め詐欺やインタネットを使った犯罪が会社名義で行われることもあることから、口座開設の審査も年々、厳しくなってきています。
資本金が1円からOKになりましたが、実際に1円で株式会社を設立したところ、某有名インターネット銀行の口座開設ができずに、泣く泣く増資手続きをされた方もいらっしゃるくらいです。
その辺りの注意点などについても、下記ページで詳しく解説しておりますので、ぜひ参考にして頂ければと思います。
法人名義のクレジットカードも作っておこう!
無事銀行口座の開設が済んだら、次は法人名義のクレジットカードも作りましょう。
今やネットでの決済はクレジットカードが大半です。
会社経費の支払いに利用すれば、会社名義の銀行口座から引き落とされますので、経理事務の効率がアップします。
最近ではクレジットカード・銀行口座と連携をさせて経理処理の自動化(勝手に記帳をしてくれる)が可能な会計ソフトも出てきています。本業で忙しいスタートアップ時には大変嬉しい機能ですね。
また、個人のクレジットカード同様、各社ポイントサービスも用意しているので、ポイントも貯まります。国内外問わず海外出張が多い仕事などですと、自動付帯で旅行保険が付いている会社もあります。利用しない手はありませんね^^v
ただ、実績も何もない新設法人ですと、与信審査に落ちる場合もあるので、予め、会社で利用するための個人名義のクレジットカードも用意しておくと良いでしょう。一時的に代用できますので。
個人名義のカードを現在お持ちでない方は、会社を作る前、あるいは個人事業で起業する方も、1枚は事業のクレジットカードを作っておくようにしましょう。
【関連記事】
設立手続きQ&A
会社の商号は自由に決めていいのでしょうか?
会社の商号は、基本的に自由に決めることができます。
商号に使える文字は「漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字・アラビア数字」と一部の記号が使えるため、これらの文字を組み合わせることで幅広いニーズに対応しています。
数字だけの商号であっても構いませんし、日本語で読めない造語であっても構いません。
だだし、登記上、同一住所に同一商号がなければ使用できますが、類似商号の使用禁止規定や不正競争防止法による規制はありますので、事前に必ず商号調査は行うようにしましょう。
事業目的を決めるときの注意点はありますか?
会社の事業目的には「明確性」が要求されています。
「適法で営利性があり、誰にでもわかりやすいこと」が求められます。
普段日常的に使用している言葉であれば、特段問題はありませんが、例えば業界用語であったり、最近使用されるようになった言葉であれば、事前に法務局へ確認をするほうがよいでしょう。
また、会社設立後に役所から許認可を受けて事業を行う場合は、許認可を受ける申請窓口へ目的にどのように記載されていれば良いのか、確認しておきましょう。
会社の住所はどこでもいいのでしょうか?
会社の住所「本店所在地」は、どこに置いても構いません。
自宅でも、事務所やレンタルオフィスを借りても構いません。基本的には実際に事業を行う場所に会社の住所を置くことになります。
注意点としては、自宅の住所を使う場合、賃貸契約で家を借りていると事業用として使うにはオーナーさんや管理組合の承諾が必要になることがあります。会社として住所が登記できるどうか事前にオーナー側に確認する必要があります。
また、役所から許認可を受けて事業を行う場合は、許認可の内容によっては、所在地や広さ等に要件が設けられていますので、事前に要件を確認してから会社の住所を置くようにしましょう。
資本金の決め方は?
会社の資本金は、設立後の運転資金です。設立直後ですと会社の規模を表す指標となります。
多ければ多いほど資金繰りに余力があることになりますので、安心して経営に取り組むことができます。
具体的には、開業にかかる費用、家賃、人件費、設備代などを計算して、当面会社を運営していく上で最低必要な金額を資本金とするとよいでしょう。
飲食店を経営するのであれば必然的に資本金は大きくなりますし、ウェブなどのフリーランスの方であれば、資本金が少なくても起業できます。
資本金の下限はありませんので、いくらでもいいのですが、あまりにも資本金が少ない会社では、会社の銀行口座が開設できなかったり、融資を受けることができないことがありますので、注意してください。
誰が出資してもいいのでしょうか?
会社を設立して資本金を出資する人のことを発起人といいますが、発起人の資格に制限はないため、基本的には誰が出資しても構いません。
一人でもいいですし、複数名でも問題ありません。ただし、公証役場で定款認証の際に発起人の印鑑証明書が必要になりますので、印鑑証明書を取得できない14歳未満の人が発起人になる場合は、公証役場に事前に確認が必要です。
また、発起人は会社設立後は『株主』となります。株主は保有している持ち株数に応じて議決権を行使したり、配当を受け取る権利を持ちますので、出資割合には注意してください。
資本金を払い込む銀行口座は新たに開設したほうがよいのでしょうか?
資本金を払い込む銀行口座は『発起人名義の口座』であれば新たに銀行口座を開設する必要はなく、今まで使っていた銀行口座を使用すれば問題ありません。
たまに会社の銀行口座を作って、そこに資本金を払い込むと思っている方がいますが、まだ会社は設立されていませんので、会社名義の銀行口座を作ることはできません。
また、『誰が、いつ、いくら出資したのか』を特定するため、預金残高では出資したことにはなりません。例えば、出資するお金が50万円で口座残高に100万円あっても、いったん50万円を引き出してから、あらためて50万円を払い込む必要があります。
資本金を払い込む銀行口座はネット銀行でも大丈夫でしょうか?
最近ではネット銀行を使用されている方がたくさんいらっしゃいます。
ネット銀行の場合、銀行通帳がありませんので、ログイン後に表示される「銀行名」、「支店名」、「口座名義人氏名」、「口座番号」が表示されているページと、「振込明細」のページを印刷したものを使用します。
振込明細ページに上記全てが表示されている状態であれば、1枚だけ印刷したもので構いません。もし印刷機能がなければ、画面キャプチャしたものを印刷しても問題ありません。
譲渡制限を付けないとどうなりますか?
株式に譲渡制限を付けない場合は、『公開会社』となります。
公開会社とは上場会社のことではありません。一部の株式でも譲渡制限を付けていない会社のことです。
譲渡制限を付けていない=会社の承認なく株主が自由に株式を譲渡(売買)できますので、会社が望まない第三者に株式が分散される恐れがあります。
また、公開会社は『取締役会・監査役』を置かなければなりません。取締役は3名以上、監査役は1名以上必要です。譲渡制限を付けていると役員の任期は最長10年まで伸ばすことができますが、公開会社では役員の任期を伸ばすことはできません。
このため多くの中小会社では譲渡制限を付けて設立します。
会社代表者印(法人実印)はどこで作ったらいいのでしょうか?
最近ではインターネットの通販サイトで購入される方が多いです。
印鑑作成専門の通販サイトでは、低価格・納期も短いため、費用を抑えて印鑑を作成したい、すぐに印鑑を準備したいという方がネット通販を利用されます。
商品を実際に見て購入したいという人は街のハンコ屋さんで購入されます。
会社代表者印(法人実印)は「一辺が10mm〜30mmの正方形に納まるもの」と大きさの規格がありますが、18mmで作成されるのが一般的です。
ネット通販でも実店舗でも好みで購入してもらって構いません。
弊社でも法人実印の販売をしておりますので、ぜひご利用ください。
設立登記完了後の手続きQ&A
会社設立後に必ず行う手続きを教えてください。
税務署・都道府県税事務所・市区町村役場の3箇所へ届出を行います。
会社が設立したことを知らせるために、税務署・都道府県税事務所・市区町村役場の3箇所へ「法人設立届出書」を提出しなければなりません。
この3つは必要最低限の手続きです。様式は各役所のホームページからダウンロードできるようになっていますので、確認してください。
当たり前ですが、それぞれ窓口が違いますので、事前にどこの窓口へ提出すればいいのかを確認しておく必要があります。
税務署へは「法人設立届出書」を提出すればいいだけですか?
税務署へはその他に提出する書類があります。
都道府県税事務所・市区町村役場へは、「法人設立届出書」を提出しますが、税務署へはその他、「青色申告の承認申請書」や「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」「給与支払事務所等の開設届書」など、会社の状況に応じて提出した方が良い書類があります。
こちらのページもあわせてご覧ください。
【参考】
会社の銀行口座は会社設立後でないと開設できませんか?
会社の登記簿謄本等が必要ですので、会社設立後に口座開設の手続きが行えます。
法人銀行口座を開設するには、会社の登記簿謄本や印鑑証明書等が必要になりますので、必然的に会社設立後でないと開設することができません。
法務局へ設立登記を申請してから登記が完了するには、1週間程度かかることがありますので、その間に口座開設予定の金融機関へ必要な書類を確認しておくことで、手続きがスムーズに行えます。
一人会社ですが、会社設立後は社会保険に加入するのでしょうか?
会社設立をしたら原則は、社会保険に加入しなければなりません。
個人事業主やフリーランスの方は、国民健康保険と国民年金に加入していたと思います。会社を設立したら、例え一人の会社であっても社会保険に加入しなければなりません。
社会保険には健康保険と厚生年金保健がありますが、どちらも会社の住所を管轄する年金事務所で手続きが行えます。
従業員を雇ったらどのような手続きが必要ですか?
社会保険と労働保険の加入手続きが必要です。
従業員を雇ったら社会保険の加入手続きが必要ですが、社会保険は加入できる条件があります。全ての従業員が加入するわけではありませんので、注意してください。
そして、労働保険の加入手続きもしなければなりません。
労働保険は、従業員が一人でもいれば加入しなければならない「労災保険」と一定の条件を満たせば加入しなければならない「雇用保険」の2つがあります。
まずは労働基準監督署で労災保険の加入手続きをして、そのあとにハローワークで雇用保険の加入手続きを行います。
社会保険の加入が会社設立後5日以内とありますが、遅れると罰則はありますか?
特に罰則はありません。
年金事務所への社会保険加入の届出は、原則会社設立後5日以内という規定がありますが、実際には5日以内に届出るのは困難なケースがほとんどです。
というのも、社会保険の加入には、会社の登記簿謄本等が必要になりますが、登記簿謄本は法務局で設立登記完了後に発行されます。設立登記の申請を行い、登記が完了するには1週間程度かかりますし、早く登記が完了しても法務局へ行って登記簿謄本を手に入れなければ、手続きを行うのが不可能だからです。
原則5日以内という規定には特に罰則があるわけではないので、登記簿謄本が入手できたらすみやかに加入手続きを行うようにしましょう。
まとめ
設立後の適正かつ円滑な事業経営に向けて、専門家(税理士・社労士等)を探そう。
このように、株式会社設立の手続きは多岐に渡ります。
このページをご覧になるまでは、会社設立手続きなんて簡単!書類作って法務局に持ち込むだけでいいんじゃん!と思っていた方も多かったと思います。ですが、そうではありません。会社設立完了後も様々な手続きが待っています。
STEP7でも開設しましたが、会社設立後も、
税務署・都道府県税事務所・市税事務所への「法人設立届」を、
役員、従業員問わず、会社から給料を払うのであれば、年金事務所への社会保険届出、ハローワークへの雇用保険関係届出(原則、役員は入れません)、労働基準監督署への労災の届出等を、
それぞれ行う必要があります。
私共行政書士は、定款作成や会社設立手続きのお手伝いはできますが、税金・社会保険・労働保険に関しての手続きは、それぞれ税理士・社会保険労務士がその専門分野になります。
会社設立後は、税務・労務の手続きも法律に則り、滞りなく、且つ、スムーズに行っていく必要があります。ただし、これから経営者となるあなたの仕事は「会社の業績を伸ばすこと」です。本業をおろそかにして、上記手続きに時間・手間を取られることは、避けなければなりませんし、経営上も得策とは言えません。
必要に応じて、税理士や社会保険労務士など専門家の力を借りながら、より良い経営環境を整えていってください^^v
弊社では、税理士・社会保険労務士など各分野の専門家の無料紹介サービスも行っております。
地域・相性・価格・年齢・性別・専門分野・人となり等、あなたぴったりの専門家を紹介させていただきます。初回相談、ご面談も無料です。
実績多数のコーディネーターがあなたのご希望を伺いますので、何なりとお申し付けください。ご興味のある方は、下記サイトからお気軽にお問い合せくださいませ。
最後に...
株式会社の設立は一人で、かつ、資本金も1円から可能になりましたから、手続きは簡単だと思ってらっしゃる方も多いと思います。
たしかに、規制緩和の流れの中で、簡素にはなりましたが、だからといって、適当に会社を作っても良いという話にはなりません。
冒頭で述べましたように、手続きに失敗したら、時間とお金の無駄になります。社長であるあなたの「時間」は何よりも大事なのです。タイムイズマネーです。
会社法の専門家になれとまでは申しませんが、「最低限の知識を得た上で会社運営に携わること」は社長の責務です。
当ページが、あなたのスムーズかつ適切な株式会社設立手続きの一助となれば幸いです。
印紙代が0円に!自分で設立するより安くなる!
【電子定款認証ドットコム】のご案内
株式会社の定款認証に必要となる印紙代4万円を賢く節約!自分で設立するより30,200円も安くなる!
年間250社以上の定款認証実績がある定款雛形(ワードファイル)もパターン別で6種類ご用意しています。現物出資にも対応。サイト内から、ご自由にダウンロードしていただけます。
事業目的検索も充実しています。あなたのお金と時間の無駄を省いて起業を応援!
お忙しいあなたの為に!株式会社設立代行サービスのご案内
株式会社設立フルサポート【業務対応地域:東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県 ※一部地域を除く】
弊社手数料(税込):88,000円
お客様総費用
弊社手数料88,000円(税込)のほか、法定費用約202,000円(定款認証手数料52,000円+登録免許税150,000円)。
※司法書士報酬(設立登記申請書類作成・提出代行)代金込み。
※定款認証手数料については、設立する会社の資本金等の額に応じ、100万円未満の場合は約30,000円、100万円以上300万円未満の場合は約40,000円、その他の場合は約50,000円となります。
ご自身で手続をされる場合とフルサポートをご依頼頂いた場合との総額比較
| ご自身(電子定款を利用しないケース) | 弊社にご依頼いただいた場合 |
|---|---|
| 約242,000円 | 約290,000円 |
サービス概要
株式会社の設立に必要な手続き全てをアウトソージング!
ご自身で全ての手続をされる場合との、実質差額はわずか46,400円です。
『株式会社設立フルサポート』は、面倒な会社設立手続は専門家に全て任せて、自身はビジネスの立ち上げに専念したいというお客様向けのサービスです。
お客様ご自身に行っていただく作業は、「印鑑証明書の入手・書類へのご捺印・資本金のお振込み」のみとなります!
迅速・確実・簡単に株式会社の設立を行いたいという方にはおススメのサービスです!
同カテゴリー内の記事
- ココが変わった!新会社法!株式会社設立5つのポイント!
- 一人会社の設立を考えている方は必見!徹底比較!一人株式会社と一人合同会社どっちがいい?
- 株式会社設立で得られる10のメリット
- 株式会社を設立するには?【株式会社を作る際に決めなければならない8つの事項】
- 会社を作るには何が必要?【会社設立に必要なもの】
- 株式会社の資本金とは?資本金額はいくらにすればいいの?
- 現物出資とは?
- 株式会社設立までの「流れ」と「手続き」を詳細解説
- 株式会社設立時の必要書類一覧&押印マニュアル
- あなたもスグに定款作成できる!1番くわしい定款作成・認証ガイド
- 株式会社の定款記載事項(絶対的記載事項、相対的記載事項)
- 公証役場での定款認証って?公証役場へ行く前に確認しておくべき8つのポイント
- 株式会社の登記事項
- 代表取締役を複数名(2名以上)置く場合の株式会社の設立手続きについて
- 未成年がいる場合の株式会社設立手続き
- 外国人の株式会社設立手続き
- 会社設立に際して許認可が必要な業種一覧
- 株式会社設立後に届け出なければならない8つの税務書類を把握しよう
- 法人成りによる個人事業の廃業届出について
- 株式会社設立後スムーズに銀行口座開設を行うための6つのポイント
- 会社設立時の貸借対照表について
- 会社設立時の株主名簿について
- 徹底比較!法人設立後に作る銀行口座はどの銀行がいちばん?
- 会社設立後に行う官公署への各種手続
- 発起設立及び募集設立 設立手続の流れ
- 株式会社設立Q&A
- 株式会社設立サービス費用
メインメニュー
Topics!!
【よく読まれている記事】
株式会社設立編
【よく読まれている記事】
資金調達・税金編
株式会社設立ガイド
起業・独立開業ガイド
定款変更ガイド
起業と社会・労働保険
合同会社(LLC)設立
一般社団法人設立
有限責任事業組合(LLP)設立
会社設立と建設業
会社設立と不動産投資
会社設立と介護事業
会社設立と農業
Copyright (C) 2019 行政書士法人MOYORIC(モヨリック) All Rights Reserved.
掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。