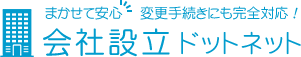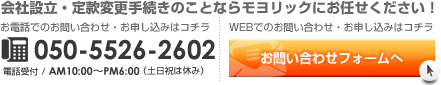株式会社を設立して人材派遣業の許可を取るために押さえておきたい9つのポイント
- 会社設立ドットネット TOP
- いちばん詳しい!株式会社設立ガイド
- 株式会社を設立して人材派遣業の許可を取るために押さえておきたい9つのポイント
【電話受付時間】AM10:00~PM6:00(平日)
株式会社を設立して人材派遣業の許可を取るために押さえておきたい9つのポイント

はじめに ~人材派遣会社設立の全手続きを解説~
人材派遣は、正式には「労働者派遣」といいます。
人材派遣会社を始めるには、「労働者派遣事業」の許可が必要です。
以前は定款の目的を「人材派遣業」としていると登記がとおりませんでした。
現在は、人材派遣業でも登記は可能ですが、労働者派遣事業の許可を受けるには、正式名称での記載が求められています。
人材派遣会社を立ち上げて、労働者派遣事業の許可を受けるには、どのような要件があるのか、どれぐらい期間がかかるのか等を確認しながら、設立手続きを進めていきましょう。
目次(もくじ)
- ポイント1.株式会社設立に掛かる費用と人材派遣の許可に掛かる費用は?
|-株式会社の設立に必要なお金
|-人材派遣業の許可に必要なお金
- ポイント2.人材派遣業の許可について
|-01. 派遣元責任者とは
|-02. キャリア形成支援制度とは
|-03. 許可基準・ 事業所の要件(広さ・所在地)について
|-04. 財産的基礎(財産基準)を知っておこう
|-05. 定款に記載する事業目的に注意しよう - ポイント3.株式会社の設立に必要となる書類は?
|-公証役場で定款認証の際に必要なもの
|-法務局で設立の際に必要になるもの - ポイント4.人材派遣業の許可に必要となる書類は?
- ポイント5.株式会社設立までの標準的な期間は?
- ポイント6.人材派遣業の許可までの標準的な期間は?
- ポイント7.派遣が禁止されている業務は?派遣期間の制限とは?
- ポイント8.許可の有効期間は?
- ポイント9.派遣法改正により「許可制」一本化に
- まとめ
ポイント1.株式会社設立に掛かる費用と人材派遣の許可に掛かる費用は?
株式会社を設立するために必要な費用はいくらかかるのでしょうか?
(1)公証役場で必要な費用
- 定款認証手数料 50,000円
- 定款に貼る印紙代 40,000円
- 定款の謄本 約2,000円
合計 約92,000円
公証役場で定款の認証を受けるための手数料は、5万円です。公証役場で現金で支払います。
定款に貼る印紙は、事前に収入印紙4万円分を購入して、定款に貼り付けておきます。定款の謄本(定款の写し)は、部数によって値段が前後しますが、2,000円ほどかかります。
こちらも公証役場で現金で支払います。
定款に貼る印紙代は、電子定款にすると0円になりますので、電子定款では合計で約52,000円になります。
※電子定款に関して詳しくお知りになりたい方、電子定款を利用して費用を削減したい方は、こちらをご覧ください。→→電子定款認証代行ドットコム(弊社の別サイトにジャンプします)
(2)法務局で必要な費用
- 登録免許税 150,000円
法務局へ登記する際に納める税金です。
登録免許税は、下記の計算方法で算出されます。
- 資本金の額✕1000分の7(0.7%)
例えば、資本金が500万円であれば、500万円✕1000分の7=35,000円ですが、この額が15万円以下の場合は一律15万円です。
人材派遣の許可に必要なお金
人材派遣(労働者派遣事業)の許可に必要な費用は、許可手数料と登録免許税があります。
- 許可手数料:120,000円+事業所が増えるごとに1箇所55,000円
- 登録免許税:90,000円
1箇所の事業所で派遣事業を行う場合は21万円、事業所が2箇所ある場合は26万5,000円になります。
これらは申請時に申請先に納める手数料です。この他、資産に関する要件「財産基準」を満たす必要があります。
ポイント2.人材派遣業の許可について
01. 派遣元責任者とは
人材派遣業を始めるには、事業所ごとに1人「派遣元責任者」を置かなければなりません。
派遣元責任者は、派遣先の企業や派遣労働者からの苦情対応や派遣労働者の就業確保・雇用管理などを適正に行う、派遣元会社の責任者です。
派遣元責任者になるには、以下に掲げる要件をすべて満たす必要があります。
<派遣元責任者の要件>
①未成年者でなく下記欠格事由に該当しないこと
・労働者派遣法等に違反して刑を受け5年を経過していない者
・破産者で復権を得ない者
・許可の取消または廃止を命じられて5年を経過しない者
・許可の取消または廃止を命じられた法人の役員で5年を経過しない者
・暴力団員等
②法律に定める要件や手続きに従って派遣元責任者の選任がなされていること
③住所及び居所が一定しない等生活の根拠が不安定でないものであること
④適正な雇用管理を行ううえで支障のない健康状態であること
⑤不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのないものであること
⑥公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行う恐れのないものであること
⑦派遣元責任者となり得る者の名義を借用して、許可を得ようとするものでないこと
⑧成年に達した後、3年以上の一定の雇用管理の経験があること
・人事または労務を担当していた者
・派遣労働者や登録者の労務を担当していた者
・職業安定行政又は労働基準行政の経験を有する者
・民営職業紹介事業の従事者としての経験を有する者
・労働者供給事業の従事者としての経験を有する者
⑨派遣元責任者講習を受講して3年以内であること
⑩外国人にあっては一定の在留資格のあること
これまでに許可の取消や廃止、罰金以上の罰則、破産暦がなければ、欠格要件に該当する可能性は低いでしょう。
また、⑨にあるように派遣元責任者は「派遣元責任者講習」を必ず受講しなければなりません。
日本人材派遣協会などの講習機関において、各地で実施されています。
厚生労働省のホームページからも講習機関と受講日程が確認できますので、派遣元責任者になる予定の人は、受講予約をしておきましょう。
派遣元責任者講習は、東京や大阪などの都市部では多く開催されますが、地方では開催頻度がそれほど多くはありませんので、余裕を持ったスケジュールが必要です。
02. キャリア形成支援制度とは
派遣元事業主は、派遣労働者のキャリアアップを図るため、計画的な教育訓練を実施しなければなりません。
これは平成27年の法改正により、新たに許可基準に追加された要件です。
派遣会社が雇用する全ての派遣社員が教育訓練などの研修を受けられるように義務付けられています。
①段階的かつ体系的な教育訓練の実施計画を定めていること
- 全ての派遣労働者を対象としていること
- 有給かつ無償で実施されるものであること
- 派遣労働者のキャリアアップに資する内容のものであること
- 雇用するにあたり実施する教育訓練が含まれていること
- 無期雇用者については、長期的なキャリア形成を念頭に置いた内容であること
②キャリア・コンサルティングの相談窓口を設置すること
- 相談窓口担当者を配備すること
- 派遣会社が雇用する全ての派遣社員が利用できること
- 希望者全員がキャリア・コンサルティングを受けられること
③派遣労働者のキャリア形成ができる派遣先の提供が行われること
- 事務手引きやマニュアルなどが整備されていること
その他、以下の内容も盛り込まれています。
- 入職時の教育訓練を行うこと
- 一定期間ごとに一定の教育訓練が用意されていること
- 毎年約8時間以上の教育訓練の機会を設けること(フルタイムで1年以上の雇用見込みの派遣労働者)
- 教育訓練を適切に受講できるように就業時間等に配慮すること
03. 許可基準・ 事業所の要件(広さ・所在地)について
人材派遣業を始めるには、事業所を設けなければなりません。
単に事業所を借りればいいだけではなく、派遣事業を行うのに適切な環境であることが求められています。
- 床面積がおおむね20平方メートル(約12畳)以上あること
- 事業所の独立性が保たれていること
- 鍵付の書庫を設けるなど個人情報保護に配慮していること
- 風俗営業や性風俗特殊営業等が密集するような地域でないこと
- 研修や面談を行うスペースがあること
派遣業の許可を申請後、後日労働局による事業所の実地調査が行われます。
事業所を借りる際には、適切な事業所として要件を満たすかどうか確認をしてから借りるようにしましょう。
04. 財産的基礎(財産基準)を知っておこう
人材派遣業を始めるにあたっては、一定の財産要件が定められています。
直近の決算において、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
<財産的基礎>
- 基準資産額が2,000万円×事業所数以上あること
- 基準資産額が負債の総額の7分の1以上であること
- 会社名義の現金・預金の額が1,500万円×事業所数以上あること
※基準資産額=資産総額-(負債総額-繰延資産+営業権)
財産的基礎は、貸借対照表又は労働者派遣事業計画書で確認されます。
設立1期目で決算を迎えていない会社は、設立時の貸借対照表で判断されますので、資本金の額がそのまま基準資産額になります。
つまり、資本金の額を2,000万円以上で設立しなければ財産基準を満たすことができません。
これらの財産基準は中小企業ではハードルが高く、なかなか要件を満たすことはできません。
そこで、中小企業に対して財産基準のハードルを低くした経過措置がとられています。以下の判断基準に該当すれば、通常よりも少ない金額で財産基準を満たすことができます。
■平成27年9月30日から当分の間の措置
- 事業所が1つであること
- 常時雇用する派遣労働者が10人以下であること
<財産的基礎>
- 基準資産額が1000万円以上あること
- 基準資産額が負債の総額の7分の1以上であること
- 会社名義の現金・預金の額が800万円以上あること
■平成27年9月30日から平成30年9月29日までの3年間の暫定措置
- 事業所が1つであること
- 常時雇用する派遣労働者が5人以下であること
<財産的基礎>
- 基準資産額が500万円以上あること
- 基準資産額が負債の総額の7分の1以上であること
- 会社名義の現金・預金の額が400万円以上あること
■中小企業に該当する企業
- 製造業その他:資本金の額(又は出資の総額)が3億円以下の会社、又は常時雇用する労働者の数が300人以下の会社
- 卸売業:資本金の額(又は出資の総額)が1億円以下の会社、又は常時雇用する労働者の数が100人以下の会社
- サービス業:資本金の額(又は出資の総額)が5千万円以下の会社、又は常時雇用する労働者の数が100人以下の会社
- 小売業:資本金の額(又は出資の総額)が5千万円以下の会社、又は常時雇用する労働者の数が50人以下の会社
05. 定款に記載する事業目的に注意しよう
労働者派遣事業の許可申請を行うには、会社の定款と登記事項証明書(登記簿謄本)の目的に労働者派遣業を行う旨が適切に記載されていなければなりません。
- 労働者派遣事業
株式会社を設立する際に作成する定款には、必ず上記目的を入れておきましょう。
(参考:人材派遣業を営む会社が定款の事業目的を定める場合の注意点)
ポイント3.株式会社の設立に必要となる書類は?
公証役場で定款認証の際に必要なもの
株式会社の設立に必要となる定款は、公証役場で公証人の「認証」を受けなければなりません。
認証とは、発起人の作成した定款が正当な手続きによって作成されたと証明することです。
この公証役場での認証手続きが終わらなければ、法務局へ提出しても受け付けてくれませんので注意してください。
公証役場は、設立予定の会社の本店(事業所)の所在地がある都道府県内にある公証役場です。管轄が決まっていますので、間違わないようにしてください。
<公証役場で定款認証に必要なもの>
- 定款原案
- 発起人の印鑑証明書
- 発起人の実印
- 4万円分の収入印紙(電子定款を利用した場合は不要)
- 公証役場手数料5万円(現金)
公証役場には、原則発起人全員が出向かなければなりませんが、代理人に委任することもできます。
代理人の場合は、追加で下記の書類が必要になります。
- 委任状
- 代理人の身分証明書(運転免許証等)
- 代理人の実印または認印
法務局で設立の際に必要になるもの
法務局には、公証役場で認証済みの定款と設立登記申請に必要な書類をまとめて提出します。
法務局へ登記申請書類を提出した日が、会社の成立日になります。
<法務局へ登記申請に必要な書類・例>
- 株式会社設立登記申請書
- 定款
- 設立時取締役の就任承諾書
- 設立時取締役の印鑑証明書
- 設立時代表取締役の就任承諾書
- 本店所在場所決議書
- 払込みを証する書面
- 別紙(登記すべき事項)
- 印鑑届出書
- 15万円分の収入印紙
上記は、取締役非設置会社の一般的な一例で登記申請に必要な書類は設立する会社によって異なります。
<その他の必要書類・例>
- 本店所在場所決議書:定款で会社の本店所在地が詳細に決められていない場合必要
- 設立時発行株式に関する発起人の同意書:定款で発起人が割当てを受けるべき株式数等を定めていない場合必要
- 資本金及び資本準備金に関する発起人の同意書:定款で資本金及び資本準備金を定めていない場合必要
- 設立時取締役選任決議書:定款で取締役を定めていない場合必要
- 設立時代表取締役の選定決議書:定款で定めて代表取締役を定めていない場合必要
- 現物出資がある場合下記の書類が必要
・調査報告書
・財産引継書
・資本金の額の計上に関する証明書
・弁護士等の証明書及びその附属書類
このように設立する会社の内容によって準備しなければならない書類が異なってきます。
定款に記載することで省ける書類もありますので、効率よく手続きを行うのであれば専門家に任せるほうがよいでしょう。
ポイント4.人材派遣業の許可に必要となる書類は?
人材派遣業を始めるには、事業所の所在地を管轄している都道府県の労働局を経由して厚生労働大臣から労働者派遣事業の許可を受けなければなりません。
申請先の労働局のホームページから申請様式がダウンロードできるようになっていますので、事前に申請先窓口へ確認しましょう。
<労働者派遣事業【許可申請】必要書類・例>
- 労働者派遣事業許可申請書(様式第1号)
- 労働者派遣事業計画書(様式第3号)
- キャリア形成支援制度に関する計画書(様式第3号-2)
- 定款(事業目的に「労働者派遣事業」と記載されていること。)
- 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 役員の住民票
- 役員の履歴書
- 派遣元責任者の住民票
- 派遣元責任者の履歴書
- 派遣元責任者講習の受講証明書
- 個人情報適正管理規程
- 最近の事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書
※会社設立後最初の決算期を終了していない法人の場合は会社成立時の貸借対照表のみ - 最近の事業年度における法人税の納税申告書(別表1及び別表4) ※会社設立後最初の決算期を終了していない法人の場合は不要
- 最近の事業年度における法人税の納税証明書(その2所得金額用)
- 事業所の使用権を証する書類(賃貸の場合:建物の賃貸借契約書)
- 事務所の配席図
- 個人情報適正管理規程
- 自己チェックシート(様式第15号)
- 就業規則
- 派遣労働者のキャリア形成を念頭においた派遣先の提供のための事務手引、マニュアル等又はその概要の該当箇所の写し
- 企業パンフレット等事業内容が確認できるもの
- 社会保険の事業所整理記号、事業所番号が確認できるもの
- 緩和された資産要件にて申請する場合
財産的基礎に関する誓約書(様式第16号)、常時雇用する派遣労働者数の報告(様式第17号)
労働者派遣事業の許可を受けるには多くの書類が必要になり、資産要件や事務所要件を満たしておかなければなりません。
確実に許可を受けたい場合は、専門家に依頼することも検討してみましょう。
ポイント5.株式会社設立までの標準的な期間は?
ご自身で全ての手続を行われる場合は、余裕をもったスケジュール設定が必要です。
法務局へ登記申請を行った日(申請書類一式を提出した日)が、会社の設立日になりますので、設立希望日があればそこから逆算してスケジュールを組むことになります。
定款を作成するのはもちろん、公証役場や法務局へも出向かなければなりませんので、効率的に進めるにはどのような作業が必要なのかを把握しておく必要があります。
会社設立までの期間を2~3週間前後みておくとよいでしょう。
ポイント6.人材派遣業の許可までの標準的な期間は?
労働局へ申請書類を提出した後、申請書類の審査がされ、事業所の現地調査が行われます。
問題がなければ、審査・調査の結果を厚生労働省に送付されます。
その後、厚生労働省において審査内容を精査の上、厚生労働大臣から労働政策審議会の諮問が開始されます。
毎月1回の労働政策審議会で許可・不許可が決定されますので、申請のタイミングにもよりますが、申請から許可までの期間は3ヶ月以上必要だと思ったほうがよいでしょう。
なお、申請に先立って派遣元責任者が派遣元責任者講習を受講しておく必要がありますので、注意してください。
ポイント7.派遣が禁止されている業務は?派遣期間の制限とは?
労働者派遣法において、労働者派遣事業を行うことができない業務が定められています。
<派遣できない業務>
- 港湾運送業務:港湾荷役の現場作業に係わるもの
- 建設業務:建設の現場作業に係るもの
- 警備業務:警備業法上の警備業務
- 医療関連業務:医師、看護師、栄養士等の業務
- 弁護士等の士業務:弁護士、司法書士、建築士事務所の管理建築士等の業務
また、派遣できる業務であっても制限なく派遣できるわけではなく、期間制限が設けられています。
(1)派遣先事業所単位の期間制限
同じ派遣先に派遣できる期間は、原則3年と定められています。
もし3年を超えて派遣する場合は、派遣先の事業所の労働組合等から意見を聴く必要があります。意見聴取した場合には、更に3年間延長できます。
(2)派遣労働者個人単位の期間制限
同じ派遣労働者を派遣先の同一組織(課やグループ)において派遣できる期間は、3年が限度となります。
同一組織ですので、裏を返せば組織(課やグループ)を変えれば引き続き派遣することはできますが、(1)の派遣先事業所単位の期間制限により派遣可能期間が延長されていることが前提です。
法改正前は、ソフトウェア開発、機械設計などの専門的な26業務には雇用期間の制限がなく、その他の業務にだけ派遣期間が3年という制限がありましたが、現在は業務内容に関係なく期間制限が設けられています。
(3)期間制限の例外
上記2つの期間制度の対象となる業務であっても、対象外となる派遣労働者と派遣業務があります。
派遣される派遣労働者が下記に該当する場合
- 無期雇用の派遣労働者
- 60歳以上の派遣労働者
下記の派遣業務に派遣する場合
- 有期プロジェクト業務:終期が明確な有期プロジェクト業務
- 日数限定業務:月の勤務日数が通常の労働者の半分以下、かつ、10日以下である業務
- 産前産後休業、育児休業、介護休業等を取得する労働者の代替業務
ポイント8.許可の有効期間は?
労働者派遣事業の許可の有効期間は、許可の日から3年間です。
有効期間満了後も引き続き労働者派遣事業を行う場合は、有効期限の3ヶ月前までに更新申請が必要になります。更新後の許可の有効期間は5年になり、以降5年ごとの更新となります。
更新手続きをせず有効期間が満了したときは、許可が更新されませんので注意してください。
ポイント9.派遣法改正により「許可制」一本化に
派遣業には、許可制の「一般労働者派遣事業」と届出制の「特定労働者派遣」がありましたが、平成27年法改正により、許可制の「労働者派遣事業」になりました。
現在は、特定労働者派遣事業の届出ができなくなっていて、許可制に一本化されています。
今まで「特定労働者派遣事業」を営んでいる事業主は、法改正後3年間は引き続き事業を行えますが、平成30年9月29日までに労働者派遣事業(許可制)へ切り替える必要があります。
もちろんこれから人材派遣業を行うには、労働者派遣事業の許可を受けることになります。
まとめ
労働者派遣事業の許可を受けるには、開業前の段階から財産的要件や人的要件を満たすか、把握しておくことが大切です。
- 財産的基礎(財産基準)を満たすことができるか
- 適切な事業所を設けることができるか
- 派遣元責任者を選任することができるか
- 適切な教育訓練計画の実施計画を定めることができるか
許可要件をきちんと把握しておかなければ、手続きが行き詰まるだけでなかなか前に進みません。
労働局へ申請してから実際に許可が下りるまでには3ヶ月期間を想定しなければなりませんので、スムーズに手続きを行うには予め労働局へ相談しておくほうがよいでしょう。
労働者派遣事業は規制が強化されていますので、許可を取得するのは簡単ではありません。
また、許可を申請するには、予め社会保険(健康保険・厚生年金保険)と労働保険(労災保険・雇用保険)に加入していなければ受理されませんので、まずは加入してからの流れになります。
社会保険、労働保険、労働者派遣事業の手続きに精通している社会保険労務士に当初から相談をすれば、大幅に手間を省略できるだけではなく、確実に許可を取得することができるでしょう。
印紙代が0円に!自分で設立するより安くなる!
【電子定款認証ドットコム】のご案内
株式会社の定款認証に必要となる印紙代4万円を賢く節約!自分で設立するより30,200円も安くなる!
年間250社以上の定款認証実績がある定款雛形(ワードファイル)もパターン別で6種類ご用意しています。現物出資にも対応。サイト内から、ご自由にダウンロードしていただけます。
事業目的検索も充実しています。あなたのお金と時間の無駄を省いて起業を応援!
お忙しいあなたの為に!株式会社設立代行サービスのご案内
株式会社設立フルサポート【業務対応地域:東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県 ※一部地域を除く】
弊社手数料(税込):88,000円
お客様総費用
弊社手数料88,000円(税込)のほか、法定費用約202,000円(定款認証手数料52,000円+登録免許税150,000円)。
※司法書士報酬(設立登記申請書類作成・提出代行)代金込み。
※定款認証手数料については、設立する会社の資本金等の額に応じ、100万円未満の場合は約30,000円、100万円以上300万円未満の場合は約40,000円、その他の場合は約50,000円となります。
ご自身で手続をされる場合とフルサポートをご依頼頂いた場合との総額比較
| ご自身(電子定款を利用しないケース) | 弊社にご依頼いただいた場合 |
|---|---|
| 約242,000円 | 約290,000円 |
サービス概要
株式会社の設立に必要な手続き全てをアウトソージング!
ご自身で全ての手続をされる場合との、実質差額はわずか46,400円です。
『株式会社設立フルサポート』は、面倒な会社設立手続は専門家に全て任せて、自身はビジネスの立ち上げに専念したいというお客様向けのサービスです。
お客様ご自身に行っていただく作業は、「印鑑証明書の入手・書類へのご捺印・資本金のお振込み」のみとなります!
迅速・確実・簡単に株式会社の設立を行いたいという方にはおススメのサービスです!
同カテゴリー内の記事
- ココが変わった!新会社法!株式会社設立5つのポイント!
- 一人会社の設立を考えている方は必見!徹底比較!一人株式会社と一人合同会社どっちがいい?
- 株式会社設立で得られる10のメリット
- 株式会社を設立するには?【株式会社を作る際に決めなければならない8つの事項】
- 会社を作るには何が必要?【会社設立に必要なもの】
- 株式会社の資本金とは?資本金額はいくらにすればいいの?
- 現物出資とは?
- 株式会社設立までの「流れ」と「手続き」を詳細解説
- 株式会社設立時の必要書類一覧&押印マニュアル
- あなたもスグに定款作成できる!1番くわしい定款作成・認証ガイド
- 株式会社の定款記載事項(絶対的記載事項、相対的記載事項)
- 公証役場での定款認証って?公証役場へ行く前に確認しておくべき8つのポイント
- 株式会社の登記事項
- 代表取締役を複数名(2名以上)置く場合の株式会社の設立手続きについて
- 未成年がいる場合の株式会社設立手続き
- 外国人の株式会社設立手続き
- 会社設立に際して許認可が必要な業種一覧
- 株式会社設立後に届け出なければならない8つの税務書類を把握しよう
- 法人成りによる個人事業の廃業届出について
- 株式会社設立後スムーズに銀行口座開設を行うための6つのポイント
- 会社設立時の貸借対照表について
- 会社設立時の株主名簿について
- 徹底比較!法人設立後に作る銀行口座はどの銀行がいちばん?
- 会社設立後に行う官公署への各種手続
- 発起設立及び募集設立 設立手続の流れ
- 株式会社設立Q&A
- 株式会社設立サービス費用
メインメニュー
Topics!!
【よく読まれている記事】
株式会社設立編
【よく読まれている記事】
資金調達・税金編
株式会社設立ガイド
起業・独立開業ガイド
定款変更ガイド
起業と社会・労働保険
合同会社(LLC)設立
一般社団法人設立
有限責任事業組合(LLP)設立
会社設立と建設業
会社設立と不動産投資
会社設立と介護事業
会社設立と農業
Copyright (C) 2019 行政書士法人MOYORIC(モヨリック) All Rights Reserved.
掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。